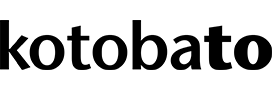写真家の藤原 新也氏の写真展『祈り』へと足を運んだ。展覧会の計画を知った去年から楽しみにしていたが、1969年インドの旅から始まった藤原氏の50年の旅が、圧巻の迫力で展開されていた。
この写真展は世田谷美術館でも始まったが、一足先に2022年9月から11月に掛けて、藤原氏の地元である北九州市にある北九州市美術館別館と北九州市立文学館で開催されていた。私は初日に訪れ、残念ながらトークへの参加は叶わなかったものの、藤原氏の出身地である門司港と対岸の下関にまで足を伸ばした。
また、10月には、NHK『日曜美術館』でも紹介されていたらしい。



藤原 新也という写真家の作品との出会いがいつだったかは、全く覚えていない。書店で雑誌か本を立ち読みしている時に見たのかもしれないし、図書館だったかもしれない。
一つだけはっきり言えるのは、たまたま手に取った、藤原氏の代表作ともなった『メメントモリ』という一冊によって、藤原 新也という人間の存在と名前を強烈に意識したことだ。著名な写真の一つである、インドのガンジス川で撮影された犬が人の遺体を食べる写真と、そこに添えられた「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」という短い一文には目と心を奪われた。嫌悪感や悲壮感、猟奇性ではなく、ただただ強烈なショックを受けた。
当初、藤原氏は、単なる過去の集大成的な回顧展には乗り気ではなかったらしい。そもそも自身の写真フィルムや著作、書についても、見直したり、適切に保管することに関心が無いと語る。
そんな中で、『メメントモリ』にも収録されいた、夜明けのガンジス川河畔に灯る光を捉えた写真を見ているうちに、「祈り」というキーワードが思い浮ぶ。一度は『祈りの軌跡』が候補だったものの、最終的に『祈り』に落ち着き、今回の写真展と書籍のタイトルになったと聞く。
同書の随所に刻み込まれた写真と文章は、どれも非常に衝撃的かつ魅力的で、放浪どころか全くの世間知らずの青年の感情をとても強く深く揺さぶった。沢木耕太郎の『深夜特急』に突き動かされた青年もいるように、私の場合は、それが藤原 新也であった。
『メメントモリ』はごく小さなサイズの本なのだが、開くといつも大きく思える。自分の手元にしばらく置かれては、その後何人かの友人の転機だったり、縁者や知り合いが亡くなった時に遺族の元へと贈ることで旅をしていった。新しい本を買って一度も開かずに誰かに渡すのではなく、なぜか一旦、自分のところに落ち着けてから渡すのが儀礼のような気がしていて、同じ一冊がすべて循環しているような不思議な感覚もある。軽々しくページをめくれないので大事にしていたが、むしろボロボロになるぐらい見返して「使い倒す」のが合っていたのかもしれない。自分自身が所有しているようでいないような、不思議な一冊でもあった。
写真展では、同書からのショットも多く、迫力ある大きなサイズのビジュアルと文字で展示されている。
また、藤原氏の著書『アメリカ』と『アメリカ日記』で使われていたショットも多く展示されていた。同書には、自分があの大国に対して抱いている複雑な感情の断片が散りばめられていたこともあり、『メメントモリ』同様に思い出深い。

私は1990年代に、出張やプライベートでアメリカ西海岸に数回、東海岸に一度行くことがあった。その時、あちこちで初めて体験した、テクノロジーへの渇望や人種格差、憧れと現実、大量消費社会、緊張感、優しさ、希望など、言語化しきれないさまざまな思いが堆積していっていた。
乾いた風景と記憶には、その景色を切り取った文章が似合った。普段なら見過ごしてしまいそうな一瞬が、藤原氏の視点とシャッターで見事に切り取られていて、まるで一緒にモーターホーム(キャンピングカー)に乗って、アメリカ横断の旅をしているような感情を抱いたのだった。


会場には、巨大な書も何点か展示されていた。藤原氏のことは、写真家というより、写真を撮る文筆家として認識していたが、イラストレーションなどの作品も展示されていた。今回初めて、藤原氏のプロフィールを詳しく見て、東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻中退というバックグラウンドを知ったので、改めて納得した。
一つの書の横に添えられた、アジアの街頭で人混みの中、巨大な書に挑む姿がエネルギッシュだ。現物の紙の上には、文字通り藤原氏の足跡もしっかりと残っている。
藤原氏と親交があった瀬戸内 寂聴さんとの直筆の手紙も、複数展示されていた。そういえば、ポッドキャスト番組では瀬戸内さんの想い出も触れられていて、亡くなる前に面会の機会はあったものの、考えた末にそれを断ったという話が語られていた。

また、自分自身の出来事についても思い出していた。20年以上前だが、縁者が事故で急逝し、葬儀に駆けつけたことがあった。故人を知る人に最期の姿をきちんと伝えなければという使命感から、遺族の了解を得て故人の姿を撮影し、一つのビデオにまとめた。しかし一人だけ、『いい想い出の姿だけでいいから、見ない』と断られてしまった。当時は『一体、なぜ!?』という憤りや落胆も覚えたものだが、歳を重ねた今なら、相手の反応だけでなく、自分の身勝手な正義感や義務感、そして本当に故人のことを自分自身が知っていたのかまで、考えは及ぶ。
肉筆の手紙からは、突然の別れではなく自身の終末を意識した瀬戸内さんと、心で深く通じ合っていた藤原氏との、魂による最期の交流の形跡を感じることができた。
別府の鉄輪にも何度か訪れたのは、藤原氏の『鉄輪』を読んで何となく記憶に残っていたことが影響していたのかもしれない。海峡で隔てられた門司港と下関、山々と湯気で隔てられた幸せな頃の記憶と将来。湿度があるどころか湯煙で満たされた光景なのだが、郷愁や惜別というウエットな感情もありつつ、それでいてどこかドライな暗さも感じずにはいられなかった。
香港の雨傘革命の取材写真では、周 庭(アグネス・チョウ)さんや黄 之鋒(ジョシュア・ウォン)さんの写真の横に、デジカメ写真の上にiPadで重ねた手書き文字のショットや、メッセージ入り付箋の壁面「レノンウォール」が再現されていた。
また、渋谷のハロウィーンでは、思い思いのコスプレをした若者に交じって、白い放射性物質防護服とマスクに身を包んだ自身の姿も写していた。
決して、新しいテクノロジーや見せ方に否定的だという訳ではなく、自身の肌感覚に馴染んで腹落ちしさえすれば、むしろそれらを積極的に活用しようという貪欲さも垣間見えた。



写真展を見た後に偶然、1991年1月発行の雑誌『デジャ=ヴュ』で、『パリ、テキサス(1984年)』の映画監督ヴィム・ヴェンダースと、藤原氏が対談していたことを知った。今回の写真展も、藤原氏の壮大なロードムービーのようだという印象を持っていたので、これは時間を逆行する素晴らしい続編になった。
藤原氏の姿を写真で見たり声を聞いたのは、ずっと後になった2000年代以降になってからのことだ。今では、ポッドキャスト番組で語りを聞くことができる。今回の写真展『祈り』の準備やその後、瀬戸内 寂聴さんとのこと、香港の雨傘革命など、写真展や写真集だけでは分からないことについても、自身の言葉で語られている。旅の副音声解説としてもお勧めしたい。
藤原 新也 写真展『祈り』で過ごした時間は、不可知論者にとってすら、人間の生命に対する静かな祈祷の時間であった。
写真という視覚言語が持つ力強さ、しかも巨大なサイズに引き伸ばされたことによる、自分との面積比による迫力。また、短く力強い文章が添えられた、メッセージの圧倒的な拡張。どの作品も全て、人間賛歌であった。人類史上、最も多くの人々がカメラを手にし、手軽に文章を発信できる現代、ソーシャルネットワークでシェアされるコンテンツとは、全く似て非なる写真と文章の数々がそこにはあった。
約2ヶ月間の会期中、機会を作ってもう一回ぐらい行ってみたいと思っていたものの、結局、一度訪れただけだった。しかしこれもまた、藤原氏の『カメラのシャッターを押すのは一度だけ』という姿勢にも通じた、自分なりの一期一会だったのかもしれないと、都合よく納得してみる。そして、写真集のページをゆっくりとめくりながら、自分なりの旅を続けていく。