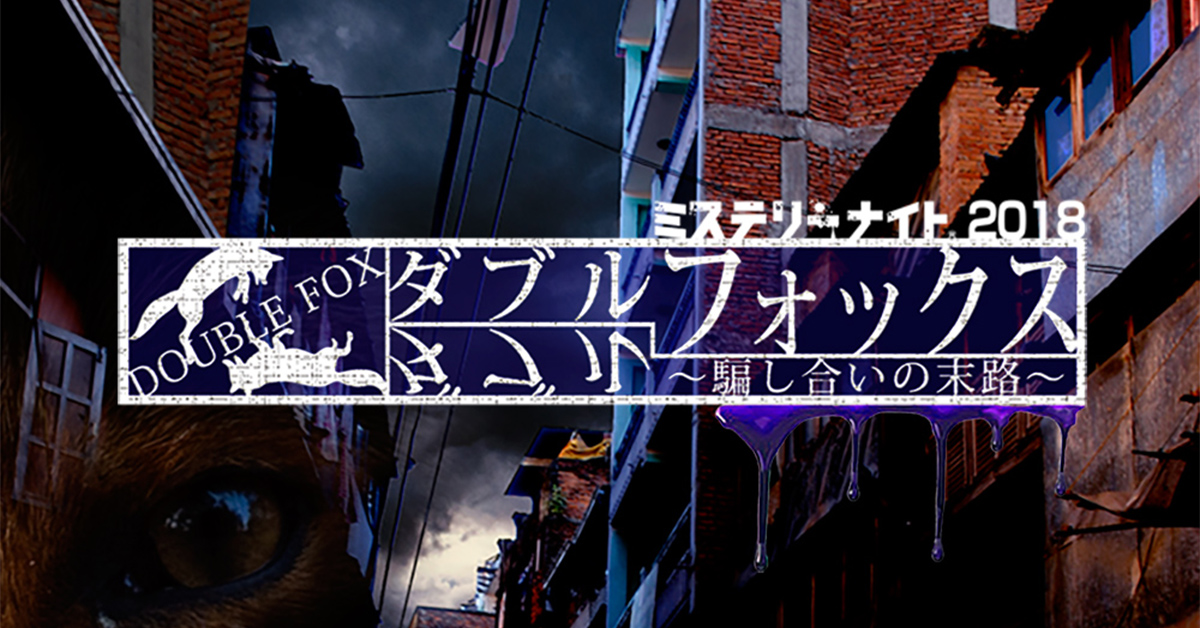先日、『ミステリーナイト 2018 ダブルフォックス〜騙し合いの末路〜』という、2日間に渡るイベントに参加してきました。「金田一募金」同様、今までしたことがなかったこの夏の体験だったので、雑感をメモしておきます。
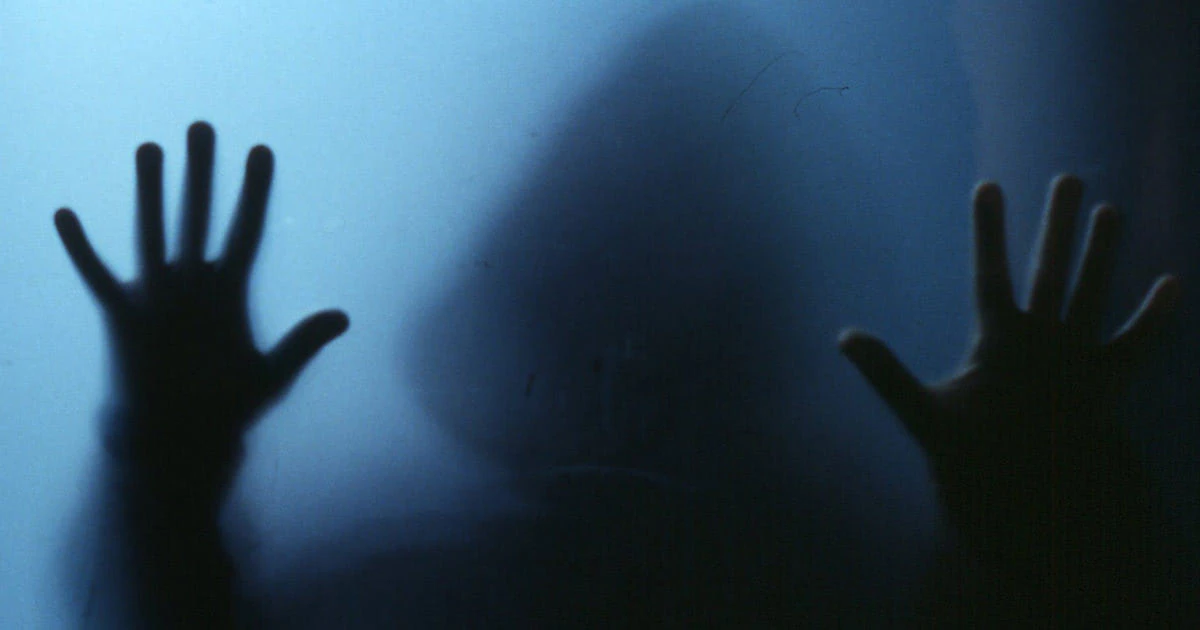
31年目の超人気ミステリーイベント

ゲーム制作者のエレメンツ石川さんに誘ってもらったんですが、これは、役者さんが演じる舞台での芝居と、施設内での謎解きゲーム、ビデオ映像などを組み合わせた、体感型推理ミステリーイベントです。
初めて知りましたが、何と31年も続いている超人気企画なんだそうです。イベントの規模は想像していたよりも大きく、キャストやスタッフを始め、制作と運営にはかなりの人数がかかわっていました。
今回は、東京、大阪に続いての福岡公演でした。近年、インバウンド客の増加で福岡市内のホテルの客室数が不足していることもあって、地元民は一旦、自宅という日常へ戻っての日程でした。以前は、ホテルシーホークで開催され、参加者は宿泊し、その閉じた非日常空間を舞台にして、繰り広げられていたんだそうです(その形式なら見聞きした覚えがありました!)。
何より驚いたのが、参加者の人数と客層。昼と夜の2回公演だったんですが、合わせて約250名もの人が客席を埋めました。遠方からの参加と思われる、大きなスーツケースを引っ張って来ている人も、何人か目に付きました。
若い人たちはあまり見かけず、おばさま達がメイン(私も似たようなものですが…)。ご夫婦やご姉妹、家族での参加もいました。会場が、ビジネスセミナーがよく開催されている薬院の電気ビルみらいホールだったこともあって、『この人たちは何のセミナーに来てる?』と思っていた人たちが、実は全員参加者でした(失礼しました!)。
後から知ったところでは、10数回も参加している熱心なファンもいるとかで、推理小説好きや探偵趣味の方、演劇好きの皆さんから、本当に根強く支持されているのだと感じました。
夏休みの読書感想文としての文脈

ストーリーに沿った推理と間に挟まれた謎解きですが、知識や瞬発力よりも、柔軟な発想力やものの見方が試されていたように思いました。「謎」と呼ばれる仕掛けも、ある程度フォーマット化されているのだろうなと感じました。恐らく、2〜3人の少人数チームで臨む方が有利でしょう。成績はスコア化され、2日目の午前中に「優秀な探偵」が発表される流れでした。2日間にまたがれば、推理を組み立てる時間は十分に取れると思いきや、あれこれ悩んでいるうちに、時間がどんどんなくなってしまいました。
初めて体感する形式のイベントだったので、いろいろなところをとても興味深く感じました。ステージ上で展開される芝居なので、リアルタイムなのはもちろん、観客の反応に応じたインタラクションや、ちょっとしたミスすらもライブ感につなげていく演出は、さすが舞台ならでは。やはり、うまい狂言回しがいる芝居やプレゼンは面白いですね。
最後の主催者説明でもいわれてたことですが、いわゆる脱出ゲーム系のイベントは、クイズやパズルを解いた上で脱出に成功するという明確なゴールが決まっています。それに対して、犯人を当てるという答えそのものだけでなく、そう判断するに至った解釈やプロセスも重視している今回のイベントは、読書感想文に似ているという話が非常に興味深く感じました。
試された日頃の集中力と柔軟性、読解力
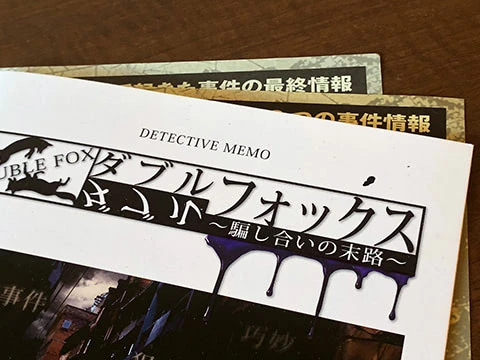
一方、思い知ったことの一つが、自分が日頃接しているコンテンツとの圧倒的な違いです。当たり前ですが、芝居の部分って、後からもう一度確認したりできないわけです(部分的に、再演はありましたが)。
タグやキーワードで検索したり、自分が見たいところまでスキップ、必要なところだけ何度もループする、ピンチインでズームする、残り時間をチェックする、再生時間をコントロールする、人にまとめてもらった情報のエッセンスだけをダイジェストで見るといった、日頃のコンテンツの見方がすべてできないんです。漢字が書けなくなっているのと同様に、日頃、実はコンテンツを注意散漫に消費しているのではないかと、本筋とは関係ない危機感も覚えました。
それならそれで、もしかするとできるだけ前の方の客席中央で、かぶりつきで見られる席の方が有利だったかも。後ろなら、オペラグラスを使うとか。慣れてる人は、速記者のようにメモしながら見てたり、深夜にチャットで相談しながら、推理結果を組み立てていたのかもしれません。
客席へ降りていくか、ステージへ誘い上げるか

広告の世界では、よくこういう喩えが使われるのを思い出しました。以前は、情報の発信者である「ステージで演じる人」と、受け手である「客席で見る人」とが、はっきり分かれていました。今は、ステージから客席へ降りていくか、ステージにオーディエンスを引っ張り上げる、または楽屋裏をチラ見せすることが、ブランドと人・人と人を繋ぐのに重要だといわれています。
予め仕込まれた見せ方と導線、ライブのハプニングすら上手く取り込み、二度と同じことが再生されないリアルな現実に対して、集中力を高める。客席も使った立体的な見せ方。芝居によって物語を見せる緊張と解説や質疑応答という弛緩、コンテンツを見るだけのパートと、手と頭を使って参加する謎解きパートのバランス。閉じた空間で、演出された世界観とメッセージをオーディエンスに届ける。そして、最後に成績優秀な参加者を舞台で表彰し、キャストも一緒に収まって写真撮影して、ファンの心を掴む。
流石は、30年以上に渡って培われたイベントでした。芝居+謎解きイベントも映画同様、今や『如何に2時間、スマホをオフにさせるだけの時間価値を提供できるか?』がポイント。『もし、自分がやっていることに活かせるとしたら、どこだろう?』『自分だったら、どうやって見せるか?』…間違いなく補講決定のポンコツ探偵に終わった私は、今、そんなことを考えています。
そして、もう一つ気付いたことがあるので、それはまた別のエントリーで!