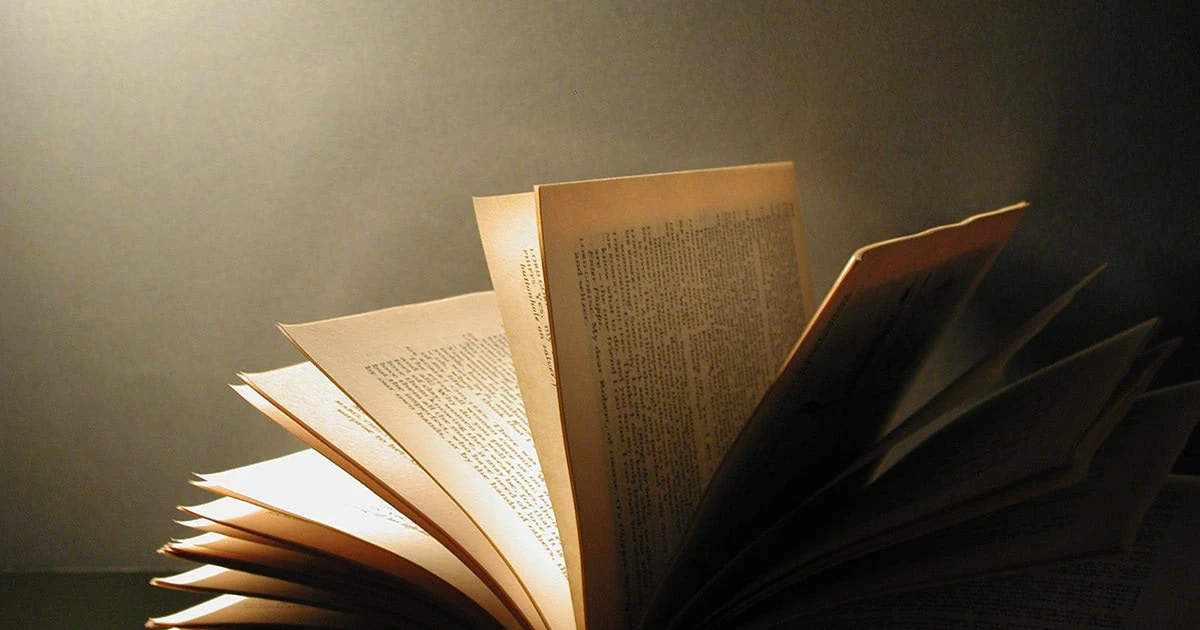
和解も何も、勝手に自分が長い間感じてきた違和感が、ちょっとだけ晴れつつあるように思っているだけだ。聞き手としても、もし語る側になった時でも、積極的に対話に参加することで物語の一部になって、自分が立っている場所からの景色を見つめたい。
その物語は、過去を都合よく書き換えてないか?問題
戦争や災害、事件・事故などの出来事を後世に伝える、いわゆる「語り部」と呼ばれる人々がいる。当事者本人の場合もいれば、家族や関係者の場合もある。被害者の深い悲しみや心の傷を受け止め、他者に共有していく。決して、その人たちの重要な活動を否定するつもりはないのだが、私はずっと、ささやかな違和感を感じていた。それはこういう理由からだ。
『他者と過去は変えられず、変えられるのは自分と未来だけだ』とは、よく言われる定番のフレーズだ。しかし、人間は自分に都合よく組み替え上書きしていくことで、過去を改変している。結局、語り部は、自分自身が咀嚼して、他者に披露できるだけの形に処理している。伝えたい・伝えられることを強調する一方、語りたくない・思い出したくない・場合によっては都合の悪いことには、敢えて触れていないはずなのだ。
その人なりの語りを繰り返しているうちに、まるで観光ガイドのように上手く、流暢に、慣れてしまう。自分が語っている姿や内容が、メディアを通じて拡がり、それをさらに本人が見聞きすることで、語っている本人すら、それが事実だったかのように自己催眠を掛けてしまう。本当のことを語っているのに、どこか嘘っぽく聞こえるのだ。
悲しみや恐怖への防衛本能とわかっていても
恐らく過去の事実が微妙に変えられているにもかかわらず、それが起きた事実のように伝えられているのではないかという、言い出しにくい気まずさのような疑問。無意識または意識的に「最適化」してしまうことで、歪曲とまではいわなくとも、いつの間にか変異しまっているのではないか。当事者本人や近くに居た人ならまだしも、実体験していない人が語り部として活動するのには、さらに違和感を感じていた。
しかし、人がもし、自分が感じた恐怖や悲しみを、感じたその瞬間と同じまま繰り返し続ければ、確実に壊れてしまうはずだ。悲惨かつ衝撃的な体験のマスキングは、人間として当然の防衛本能だ。頭ではそうわかっている。そのことが、さらに複雑な感情を懐かせ続けてきた。
私の身内には、戦争体験の語り部が実際にいる。しかし、私たちは子供の頃、祖父母の世代の人たちに戦争体験を聞こうとすれば、大人たちから『そんなことを聞くものじゃない』という、はっきりしたまたは無言の壁を感じて育った。この矛盾も、自分が長い間、こういったことに関心を持ち続けてきたきっかけのひとつかもしれない。
そんな中、とある2つのコンテンツが、自分の中で偶然リンクした。

