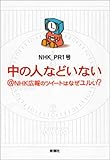7月末に起きた、インド洋モーリシャス島沖の大型船座礁事故による燃料油の流出と、深刻な海洋汚染がニュースになっています。モーリシャス島の場所がよく分からなかったので、Googleマップで探してみましたが、そこをきっかけに、関係各社のWebサイトやソーシャルメディア上での対応が目に付きました。
ソーシャルメディアの運用では、他社の事例が参考になることは多く、成功例はスポットライトを浴びてよく紹介されます。ただ、実は失敗にこそ、学ぶべきポイントが多数あります。今回の事故後の対応を、失敗だと決めつけるのは早すぎますが、これをテーマに、自社のソーシャルメディアの運用を見直してみませんか?
楽しかったパーティーは、突然終わることも…
無料で気楽に始められて、知識がさほどなくても簡単、広告の代わりだと誤解されているソーシャルメディア。御社は、貴店の認識や状況はどうですか?
ソーシャルメディアを運用することがどういうことを意味するのか、何を目的とするのかは、非常に重要であるにも関わらず、壮大すぎたり面倒臭すぎて、おざなりにされがちです。B2B(企業間取引)やB2C(企業と個人)の違いにかかわらず、オーディエンスとの信頼関係を築いていくという課題は同じですし、町の飲食店なども共通したテーマを抱えています。
日頃からすること/しないこと、緊急時にすること/しないことは何なのか?本当に守るべき価値とは何か?すべてに対応はできなくても、まったく何もなすすべがないわけではないはずです。ノウハウやルール、ツールを継続的にアップデートし続ける、具体的なリソースの確保が非常に重要です。
- ソーシャルメディアはそもそも、何のために使っているのか?
- ソーシャルメディアを使っていなければ、ネットの炎上は防げるのか?
- 自社が問題を起こした場合どうするか?顧客だったら?発注先だったら?
- 謝罪文をWebサイトに掲載する時、PDFがいいのか?テキストのままが妥当か?
- 一方的な情報発信に徹し、コメントは閉鎖した方が、場が荒れずに済むか?
- いくつかのチャンネルを閉鎖または削除すべきか?
- 寄せられるコメントにできるだけ・できる範囲で回答すべきか?
- 経営層や取引先の了解が得られたことだけ投稿すべきか?
- 有事を想定した対策チームが準備されているか?本当に機能するのか?
以下で、モーリシャス島の事故を例に見てみますが、この記事を最後まで読んだ後、もう一度上記の部分を、自社や自分に当てはめて考えてみてください。
顔が全く見えない長鋪汽船
事故の経緯や現状については、信頼できるソースを参照しておきます。
長鋪(ながしき)汽船(株):事故を起こした船を所有している(グループ会社)の親会社であり「船主」
(株)商船三井:長鋪汽船の船と船員をチャーター(外注)していた海運企業
これらの基礎情報を踏まえて、まず長鋪汽船のWebサイトとソーシャルメディアを見てみます。
- 会社概要や代表者の情報がない。
- プライバシーポリシーがない。
- ソーシャルネットワークを運用していない。
- 事故について、最初にブログ記事が公開されたのは8月8日。その前は、2019年。8月19日(水)時点で、第7報まで公開。

事故の件について、Webサイトのファーストビューでは何も表示されていません。第一の責任がある組織であるにも関わらず、情報発信のチャンネルがブログだけで、当然コメントは受け付けなし。トップの顔も見えません。ソーシャルネットワークという対話のチャンネルを持っていないことで、ステークホルダーからの理解も得にくい反面、炎上の場もないともいえます。
しかし、ソーシャルネットワークという捌け口がない市民の怒りがどこへ向かうかというと、Googleマップなんです。この場合、ローカルビジネスを運用しているか、B2Cかどうかは関係ありません。
クチコミと☆を見てみると、その大半が今回の事故以降に投稿されたものだとわかります。クチコミが15件以下または一度もしていないユーザーもいます。
特徴的なのは、海外ユーザーもいること。事故が起きたのが海外で、世界的に報道されたことの影響を考えれば、当然かも知れません。報道機関の写真をアップロードし、著作権を侵害しているユーザーもいました(Googleに通報済み)。
Googleマップのコメントは、行き過ぎだとも思える過度の誹謗中傷や個人情報入りでもない限り、非難や批判を削除できません。
商船三井の方が目立つ分、矢面に
次に、商船三井のWebサイトとソーシャルメディアをチェックしてみます。
- 事故について、最初にプレスリリースが公開されたのは8月7日(日本語と英語)。PDFではないのと、燃料油流出の翌日なので、まだ早い方か。8月19日(水)時点で、5回目のリリースを公開中(海図は長鋪汽船と共通なので、同社に提供した可能性あり)。
- ソーシャルメディアは複数運用はされているものの、対話や傾聴のチャンネルではなく、一方的な発信のみ。
- 事故の直接の責任は長鋪汽船にあるにも関わらず、商船三井のチャンネルに非難や誹謗中傷が殺到。
- 定型のパターンだと、経過報告と謝罪はWebサイト中心で、他はほとぼりが冷めるまで放置。忘れられた頃に静かに再開(こちらも、忘れられることはないが)。
Facebookは、ローカルスポットはあるものの、Facebookページはありません。というか、あるにはありますが、2019年の採用情報について日本語のみのためか、コメントは今のところなし。
一方、Instagramでは、Facebookと同じ事故には無関係の最新の投稿に、いろいろな言語で非難が寄せられています。
YouTubeチャンネルはコメントオフ。
LinkedInは、8月14日になってようやく事故について英語で投稿されましたが、早速、『組織としての道義的責任に応えているのか?』的ツッコミが入ってます。この後は恐らく、Webのプレスリリースの転載でしょう。
そして、こちらもGoogleマップのコメント。国内各地に支店がありますが、東京本社に日本語の批判が集まっています。
メディアや一般の人は、大きくてわかりやすい組織を非難しやすいのでしょう(しかも日本国内のメディアは、なぜか「商船三井」を前面に出していますし)。過去にも積荷の事故を起こしていたことも、調べればわかります。
リソースが限られている長鋪汽船はともかく、商船三井は、被害の当事者であるモーリシャス島関係者にもメッセージが届くように、フランス語と英語、日本語で細かくメッセージを出すべきか?いや、そんな余計なことをすれば、過度の責任まで認めて抱え込むことになるのでは?
分業になっている複雑さも相まって、こちらも対応が本当に難しいところです。
ソーシャルメディアがなくてよかった?あったから炎上してる?
現状の両社は、ソーシャルジャスティスウォーリアーと呼ばれる、社会的正義を御旗に敵を糾弾する戦士たちによって、度を超した誹謗中傷に晒されているはずです。恐らく現場には、クレームの電話(もしかするとFAXや手紙も)が殺到しているでしょう。直接のステークホルダー(利害関係者)ではない、不満を抱えている人たちにとって、反抗しない、叩いても構わない対象を徹底的にタコ殴りにする高揚感は、何者にも代えがたい娯楽の一つですから。

当たり前ですが、ソーシャルメディアのマネージメントが上手くいっていれば、事故が避けられた訳ではありません。Instagramのフォロワーが多い蕎麦屋が、蕎麦が旨くて、いい蕎麦屋だとは限らないのと同じです。蕎麦屋の本分とは、旨い蕎麦を、客に妥当な価格で提供すること。海運業者なら、顧客から預かった荷物を、安全確実に届けることでしょう。
さまざまな場所でシェアされた情報や書き込まれたコメントも、漏れ出した燃料油同様に、一部は洗い流されてキレイになるかもしれません。しかしそれ以外は、長い期間を漂って黒い痕跡を残すことになります。今後は、事故の補償はもちろん、株価への影響や株主への説明責任、人材募集など、両社への影響は徐々に広範囲に及んでいくはずです。B2Bビジネスにとって深刻なのは、取引先がリスクを避けるために契約を停止・回避したり、保険料が値上がりすること。銀行との交渉や、従業員の士気にも影響するでしょうし、乗組員の教育コストも必要なはずです。賠償金を支払って事業を継続できるだけの体力があるか?というネガティブインパクトかもしれません。
ソーシャルメディアを運用していなかったり、一方的な情報発信だけに限定していることが、両社にプラスになっているか、今後の信頼回復にポジティブな効果をもたらすかは、現時点ではわかりません。ただ、十分な説明責任のためには、丁寧な情報発信が不可欠です。そのためには、各ステークホルダーの窮状や意見、感情に真摯に耳を傾け続けることが必要なはずです。
一般の企業や小規模ビジネスにも、いつトラブルが発生するかはわかりません。大規模災害、納品した製品の瑕疵、法令違反、異物混入や製造ミス、搬送中の事故、アルバイト店員の悪ふざけなど、リスク要因を考えればいくらでもあげられます。
では仮に、ネガティブ情報が広がらないように、ソーシャルメディアを一切使わないことが、組織やステークホルダーにとって得策なのか?使うとしたら、目的は何なのか?どのような態度で臨むべきか?何を守るか?9月1日の防災の日も近い今、ソーシャルメディアの使い方についても、見直す機会が必要かもしれません。