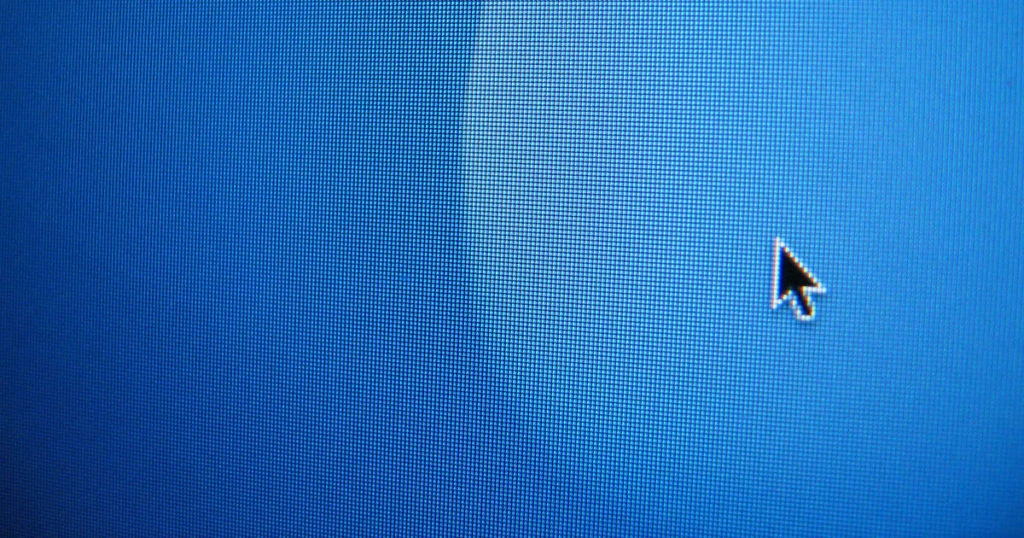
Mighty Mouseのスクロールボールの件は様子を見るとして、しばらく使ってみていろいろなことを考えました。
360度ぐるぐるできるスクロールボールは、マウスの中心線上にあります。左右のボタンにあたる部分のちょうど真ん中ですね。しかし、それを操作する手は左右対称ではないわけです、当たり前に。人差し指だろうが中指だろうが、右利きだろうが左利きだろうが。両側からつまむサイドボタンにしても、左右対称の位置にあるものの、マウスを握る親指と薬指の位置は左右同じポジションではありません。
しかし、使う人間がそれに合わせることで、(ある程度)どのような人でも簡単に使うことができる仕組みになっています。もちろん、それは無理な使い方を強要するようなものではなく、使い手の側が歩み寄れる範囲です。
Appleはその昔、人間工学のノウハウを取り入れたキーボードで、Apple Adjustable Keyboardという製品を作っていました。「エルゴノミクス」というキーワードがややもてはやされた感も、なきにしもあらず。キーボードが中央から左右に2分割されていて「ハ」の字に開く構造でした。この開き具合を変えることで、手首や腕に負担の掛からない状態に自由に調整できるという触れ込みでした。現在、この人間工学キーボードの分野で精力的に製品を作り続けているのはMicrosoftだったりします。
私は良く、この手の『何だかよく分からないけれど、使ってみたい!』感覚に騙されます。モーターショーのコンセプトカーがやたら素敵に見えるのにも通じています。一票を投じることで、接しているような気になりたい。
そう思って、発売と同時に幕張メッセのMACWORLD EXPO会場で買ったものの、実際に使ってみると、Apple Adjustable Keyboardにはいろいろなマイナス要素がありました。メカニカルな構造は、場所を取ってホコリが溜まりやすかったですし、小さな手の日本人の私には、開いた状態でのスペースバーまでの距離が少し遠かったこともあって、劇的に肩凝りが改善された記憶はありません。
狭い机の上を占拠する見た目のごつさや、標準キーボードと比較してかなり割高な価格設定、そして何よりも緩いふにゃふにゃしたキータッチと、製品発表のたびにキーの位置が微妙に変わるという当時のApple製キーボードのマイナス要素もあってか、残念ながら商業的には成功しませんでした。
しかし、それでも方向性は決して間違っていたとは思いません。「誰でも使いやすく」するために最大公約数的なところに落ち着いていくと、「私が使いやすい」ところからは離れていくかもしれません。かといって、逆にカスタマイズの自由度を上げると、複雑な構造になって製造コストに跳ね返ったりする訳です。そして、どうせならカッコよくて綺麗なモノを使ってみたい。
入手しやすと、使いやすさと、そして美しさが共存できる可能性がある製品なら、これからも小さな一票を投じて行く気がします。酷く騙されない範囲で。
そうそう、東京お台場の日本科学未来館にある、コンピューターの入力装置の歴史なんかも、面白いんですよ。昔のマウスは、今とは逆にコードが下から伸びていたそうです。確かに、そっちの方がネズミっぽいんですよね 😀


