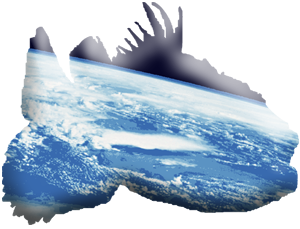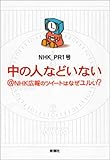「平成28年熊本地震」の発生当初から、くまモンのTwitterアカウント @55_kumamon がなぜ何も発言しないのかが疑問だった。その後発表された説明には、本当に落胆させられた。『ソーシャルでの活動は被災者の役に立たないので、最優先にするほど重要ではない』という降伏宣言だったからだ。

まさか自分の身近な土地がこれほどの大災害が起きて、「被災地」と呼ばれる日が来るなど、想像もしなかった。今まで経験が無い激しい揺れと夜中に続く余震、否応にも不安を煽る緊急アラームの重奏が、災害を「自分ゴト」にしてしまった。犠牲になった方々とそのご家族には、謹んで哀悼の意を表したい。
私は、ソーシャルメディアアカウントを運用する仕事の参考として、災害や大きな事件、事故が起きた場合や後から、関連アカウントがどのような言動をしているのかを観測したり、調べることが多い。それぞれのアカウントは、組織の考え方や運用方針によって大きく異なり、見事な運用もあれば、残念な例もある。その時、一番大きな要素は、最後は人だと常々感じている。
国内外で大人気の熊本ご当地キャラクターがどう行動するのかも、非常に気になっていた。元々、決して「ゆるキャラ」ではない「戦略キャラ」、つまり本来の意味で「キャラクター」だからだ。情報が、今や重要なライフラインの一つであることは言うまでも無い。
しかし、次のような公式発表には、サプライズではなく軽いショックを受けてしまった。
SNSでの情報発信について 2016年04月15日
くまモンオフィシャルホームページ
現在、くまモンの公式SNSでの情報発信が行われない事により、くまモン隊の安否について多くの皆様にご心配をいただいております。
くまモン隊は、この度の地震に見舞われた方々の事を最優先に行動しているところであり、SNSでの情報発信については控えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
「くまもとサプライズ」ではなく「くまもとサイレンス」。くまモンの沈黙に落胆したというより、『あの戦略キャラクターですら、そうせざるを得ない程の酷さなのか』と打ちひしがれたと表現するべきなのかもしれない。ハッピーな時限定の観光PRキャラ止まりだという「降参」にしか感じられなかったのが、悔しいのだ。
もちろん、組織のブランドアカウントの運用スタイルにはいくつかの考え方がある。例えば、ファンと積極的に対話をするアカウントもあれば、コミュニティーとしての場を演出することに徹した発信のみの運用もみられる。キャラクターを立てる場合も、一人で管理運営したり複数のスタッフで共有したりと、ガイドラインの幅による「中の人」の見え隠れ度合いでテイストが異なる。
まして、今回の地震は緊急事態だ。より重要な人の生命と安全に関わる他の任務があることや、現場に人手が足りない現実、情報の入手経路が制限されていることで、やりたくてもできないのだろうことは十分想像できる。
それでも敢えていいたいのは、地元の人たちが不安に打ちのめされ、国内外のファンが注目している緊急時だからこそ、くまモンには、信頼できる熊本の大使としていつもの活動をすべきではないのか。オンラインだけでも、今からでも。
しかし、こういっている自分自身にも、本当はどうすれば正解なのかは分からない。なぜなら、「べき」を使いたくなる時こそ、自問してみるべきだからだ。
5年前の東日本大震災の時、公式アカウントとして歴史的な役割を果たしたNHKのTwitterアカウント @NHK_PR(NHK_PR1号)の言葉を、もう一度振り返っておきたい。
P.183
いったい私はどうするべきだったのでしょう。
今でも私にはわかりません。けれども、このときの気持ちを、きっと私は一生忘れることが出来ないでしょう。
装丁や文体、切り口はまさにユルいものの、著者の中心には揺るぎない覚悟を感じる。その覚悟も、最初から確立されていた訳ではなく、失敗や手応えを感じながら徐々に成長していく育てゲー視点でも読めてしまう。大組織のソーシャルメディアアカウントがひっそりと非公式に(!)始まり、やがて公式デビューを果たす流れは、ノウハウが限られていた2010年から2011年当時の状況だから可能だったことだろう。
今はすでに、組織のソーシャルメディア運営ノウハウが(玉石混交ながら)巷に溢れかえっていて、小手先のマニュアルに踊らされては、なかなかこういったストーリー展開にはなり得なかったのではないか?誰もが経験し得なかった東日本大震災を契機に、日本でよりSNSに注目が集まった中、手探り続きながらこのアカウントが果たしてきた役割は、非常に大きいな意味を持っている。
さらりと読めてしまう書き方ではあるものの、行間には、企業に属する労働者としての責任や、報道メディアであるジレンマなどが見え隠れする。匿名実名で寄せられる罵詈雑言にしても、書籍としてキレイにまとめられている時にはクリーニング済みだ。これが単なるノウハウ本であるはずもなく、結局は、個人の「人間力」が試され続ける、実はハードな話だとも読める。その意味でこの本は、本を読んだだけでは完結しない。実際のTwitterアカウントと照らし合わせて初めて「みなさまと家族になりたいアカウント」が立体的に見えてくる。