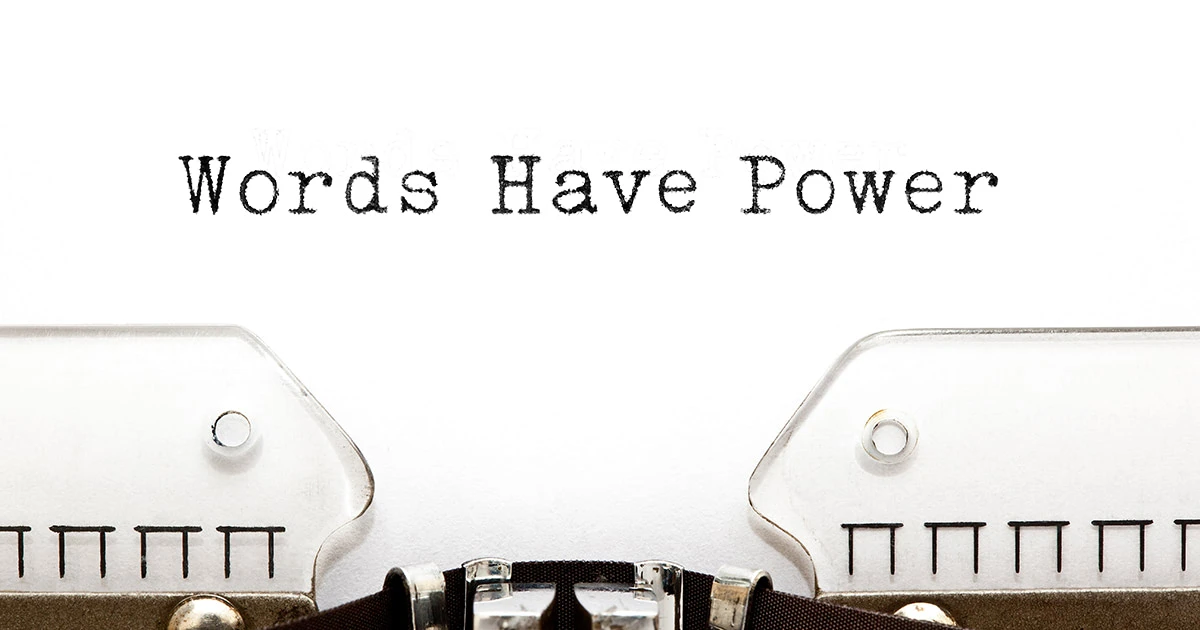たまには仕事のことも書いておきますか。「共創型ビジネスデザインファーム」である、bridgeさんのWebサイト用に連載テキストを書かせていただき、先日公開されました。ぜひ、ご一読をば!
「共創型ビジネスデザインファーム」とは?bridgeさんは、企業から信頼されるパートナーとして、そこに関わる人材や組織そのものを活性化させるプロフェッショナルです。ノウハウやナレッジを提供し、課題解決とプロジェクトの成功を通じて、それまでにない新たな価値創造を支援する企業です。このような組織があることは初めて知りましたが、なるほど、今までにない、しかしこれからますます重要なミッションなのかも。
そもそもbridgeさんとのご縁は、私がお世話になっている福岡のブランディング企業Bulancoさん経由でお話しをいただいたのがきっかけです(西中洲界隈はいいところ<3)。
今年の9月に一旦、bridgeさんのブログ記事を30本ほどリライトさせてもらっていました。嬉しいことに、テキストの質やスピードに非常にご満足いただけたようで、しばらく時間を置いて、改めてのご指名をいただいた次第です。
まるで、一つの仕事が終わったときに、クライアントから『今度、ぜひ飲みに行きましょう!』といわれたのに対して、『はい、ぜひ!』と返していたら、『で、いつにしますか?新宿でいいですか?』とでも即答されたような、思わぬありがたさでした。本当に、このままお伝えしたほどw
反射板であり、翻訳者兼仲介者としてのライティング
私は、bridgeさんが主導していらっしゃる、企業内起業や新規事業のイノベーションというリアルな現場こそ知りません。ただ、ビジネスモデルキャンバスやカスタマージャーニーマップ、ペルソナといったフレームワークや、デザイン思考にアート思考、ロジカルシンキングなどのマインドセットは、マイクロでニッチなレベルながら、私の仕事にも関係があり、まったく初めて見聞きすることでもなかったので、その点は助かりました。
また、今年の10月から受け持たせてもらっている、九州スクール・オブ・ビジネスさんの授業でも、学生さんたちにフレームワークとマインドセットの概要について説明するシラバスを作っていて、そのタイミングが偶然ピッタリだったのも幸いでした。
実際に私がしたことは、特別なことではないんです。ライターさんなら、ごく当たり前のこと。
まず、提供されたテキストやPDF、ビデオ資料をチェックし、必要なことを追加リサーチ。コロナ禍の制約だからというわけでもなく、福岡から東京へのWeb会議で経営層のお話を聞きつつ、疑問点やニュアンス、私の解釈や提案などを交えながらのインタビュー。それを元に、ちょっとしたエッセンスを加えたり構成をアレンジし、検索や回遊動線を意識しつつ、しばし寝かせては編集しながら再構成しただけです。
つまり、テキストを書いたのは確かに私ですが、その元ネタはもちろん私じゃなくbridgeさん。私は、クライアントが伝えたいメッセージをアウトプットする上でのリフレクター(反射板)であり、トランスレーター(翻訳者)、ささやかなメディア(仲介者)です。ちょっとだけ自己主張を交えたイタコ化は、ライティングあるあるですから。
文章ぐらい、誰にだって書ける!と思われているから…
そもそも、コピーライティングで扱う「テキスト」というコンテンツは、プログラムや音楽、写真、イラストレーションよりも、扱える人の総数が圧倒的に多いのが当たり前です。日本語を含む言語で文章が書ける人なら、誰にでも書いたり編集できます。そう誤解されているとしても、現実にそうなっている。
私が過去にクライアントからいわれた酷い例だと、『てにをはだけ直してくれれば十分』のようなこともありました。予算や時間がないとか、外部に依頼するのが面倒という理由で内製されるのもごく一般的です。そうやって、酷いときにはまるでキリンの身体にゾウの頭を乗せ、シマウマの模様を纏ったクリーチャーのような文章が、生成されることもありました。創造主は、時に残酷であり、無自覚。
そんなことで人と人とのコミュニケーションがスムーズに進まず、無駄なストレスが溜まるぐらいなら、ビジネス文章はAIが生成した方が遙かに効果的だと思っています。
人が文章を書く必要がなくなったとしても
実際、今年は、高精度な最新AIであるGPT-3がたびたび話題になりました。人が読んでも自然なレベルで文章を自動生成したり、フェイクニュースの乱造工場になる懸念が指摘されました。個人的には、AIが効果的な文章を自動生成する未来には、大きな期待と、若干の不安を抱かないではありません。
私は、AIが書ける・書いた方がいい文章は、そのままAIに任せていいと思っています。実際、そうなるし、止められません。じゃあ、どうやってそこから成果や利益を上げていくかというと、それはまた悩ましい問題ではあります。
それでもやっぱり私は、何かを書き続けていくんだろうと思っています。意味があるか、読者に読まれるかどうかに関係なく。
新型コロナウイルスの影響で激動の日々だったこの一年。個人的には、テレワークの急速な普及やワークスタイルの変化によって、言語化・テキスト化の意味が少しシフトしたように感じます。また、Web会議の小さな画面のじれったさを通じて、バーバルとノンバーバル両方のコミュニケーションの必要性も、再認識されたように思います。
私が仕事で書いているテキストのほとんどは、記名で公開されることがなく、完全に裏方です。ライブではなく、作り込みのコンテンツなので、クライアントやユーザーの反応を直接知る機会もほとんどありません。そんな中で、クライアントからのご用命で、さらにご指名のリピートがあるというのは、とてもありがたいことです。本当に感謝、感謝。ちなみに、bridgeさんの記事は、この後2021年の1月末と2月末にも公開予定です。
御社のテキストも書かせてもらえませんか?一般企業やメディア、小規模ビジネスから個人の皆さんまで、幅広くご相談を承ります。また、ライティング講座も開催しています。ソーシャルネットワークでも、どうぞお気軽にお声掛けください 😉