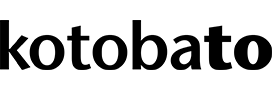福岡市中央区六本松にある「古書の葦書房」が年内で営業終了だと知ったので、久しぶりにリアル古書店に立ち寄った。
店の前の狭い路地はよく通っていたが、店内に入るのは初めてだった。2年前の夏に近所から移転して来た店舗だが、元の店に数回行ったことがある程度だ。店内は、閉店を知って来た客で少し混雑しているようだ。一歩足を踏み入れると、狭い空間に積み重なった、枯れた光景や懐かしい匂いが押し寄せる。
大きな書架と人に挟まれた細い通路を、縫うように彷徨う。目に入る多くの本はバーコードや奥付もなく、発行の詳細が分かりそうにない。背表紙が無い簡易冊子や、修復途中と思われる民俗資料も豊富に並んでいる。自分が読んだことがある本が数冊だけ目についたが、まるで誰かに再会したような、気まずい複雑な気分になった。お互い決して若くもないし、とはいって枯れているわけでもない姿を見て、懐かしい以外に特に話すことが思いつかない、そんないたたまれなさだ。
何年も前から、そこに確かにあったのに、自分には縁がなかった本。自分はこれら先人の叡智のほとんどを一生知ることがないのだろう。録画するだけして見ていない映画、書いて出さなかった手紙、下書きのまま捨てたメールと同じ。誰かが伝えたかったメッセージの大半は、その思いを遂げることなく忘れ去られる運命にある。
気まずさの理由は他にもある。背表紙がどこか墓標に見えるのだ。
それはここ数年、自分が買った古本は片っ端から断裁して電子化しているからだろう。最初から電子書籍で買えるならそちらを選ぶので、紙の本をそのまま読む機会は限られる。いつの頃からか、私には古本や古書を扱う書店が、まるで墓地のように感じられるようになった。霊場巡りもこんな感覚なのだろうか。
誰かが書いていたが、紙の本の電子化は食肉解体処理にとても似ている。皮を剥ぎ、背を割り、骨を外して、肉を細かく削いでいく。可食部分以外は、処分に回される。かつて自分も少なからず「生産者」側だった身にも関わらず、私はパッケージにはほとんど未練を感じていない。
ふと、「アーカイブ」という言葉が古文書の意味だったことなど思い出す。ここにある大量の本は、この後どこへ行くのだろう?働いている人たちはどうするんだろう?ぼんやりと思いを巡らせる間にも、客が入れ替わっていく。閉店を新聞で知ったという客が来れば、自分の名字と家系について聞く老婦人がいる。場所を尋ねる電話も掛かってくる。
つまり、ここはそういう場所だったのだ。変化する必要のない自分のスタイルで、メディアのフォーマットに追随しない、固定された知識を求める人たちの安息の地なのだ。ここには、「コンテンツ」呼ばわりされることを望んでいる本が一冊も無い。アップデートも、シェアも、コメントも求められていない。そんな場所を自発的に離れたにせよ、追い出されたにせよ、たまにこういう場所に戻って感じる懐かしさと安心はどこから来るのだろう。
ともすると最近は、話題になったりレコメンドされただけの理由で目に付いた本から、自分に役に立ち、しかも即効性がある本を選びがちになる。高速で駆け巡るインフォメーションを消費している。選んだつもりが選ばされている気もする。多感な頃を振り返れば、古本屋で偶然見つけた書籍や雑誌、カタログから自分が強い影響を受けたことが少なくない。それは恐らく、新刊の書店では出会えなかった貴重な体験だ。ノイズの中にビートを感じた。今とは違う新しい発見の芽は、実は最先端ではない身近な場所に点在しているのかもしれない。
店主は、閉店間際に慌ててやってきた客たちの、あやふやで面倒な問いにも次々に答えている。本当に興味深いのは、ここに並ぶ本そのものではなく、間違いなく彼の語りだろう。人こそがアーカイブ。
紙の表紙を触りながら、昔、古本屋の店主に少し憧れていたことを思い出した。近所にあった古本屋の初老の親父は、会計と値付け、たまの商品陳列をやるぐらいで、起きているのか寝ているのか分からなかった。それも実は、子どもには分からないだけで、商品の選択や客あしらいの眼光は鋭かったのだろう。
新しいものはいずれ古くなるが、古くても残ったものは深くなっていく。

朽ちていくパッケージの悲哀や、伝わらなかったメッセージの無念さを霊感豊かに感じ取ったりはしない。ただ、かすかな罪の意識とノスタルジーが拭えないことを思い知る。きっと、自分は何かまた別の形でここへ戻ってくるのだろう。透明な血で汚れた指先で、そっと紙の表紙を愛おしんで店を後にした。