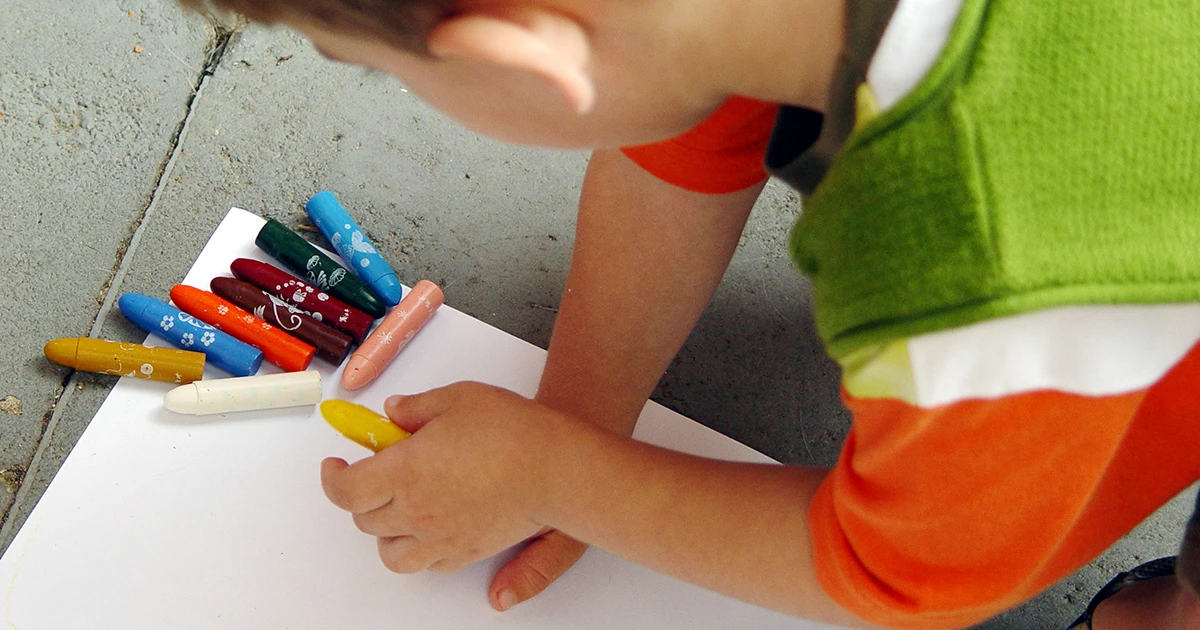この2年半ほど関わらせてもらっていた、福岡市内の専門学校Adachi学園さん(九州ビジュアルアーツ/九州スクール・オブ・ビジネス)での授業が終わりました。元々、校長先生と知り合いだった縁で声を掛けてもらいましたが、関係者の皆さんには本当にお世話になりました。ありがとうございました 😀
20歳前後の複数の人たちに定期的に接する機会は久しくなかったので、この機会に自分の経験や感想を整理しておきます。ただし、AIテキストジェネレーター「ChatGPTとの雑談」という形式で。
街で大人気!クレバーだけどちょっとクレイジーなアイツ、ChatGPT
ChatGPTは、AIによる対話型のテキスト生成サービスです。大手テックベンチャーであるOpenAIが開発する、GPT-3.5という大規模な言語モデルが使われています。
2022年11月末に公開されたChatGPTは瞬く間に大人気になり、初夏から大ブームになっていたAI画像生成サービスを遙かに凌ぐ話題で、今も新しい情報が日々溢れています。今や地上波テレビでも紹介されるほど話題沸騰になっているというわけ。
そもそも、ChatGPTに使われている言語モデルGPT-3.5は、一つ前の世代のGPT-3をチューンナップした言語モデルです。私は2022年の秋頃から、GPT-3を使った文章の(半)自動生成AIサービスをいろいろ試してきました。結果は、想像以上にボロボロ。GPT-3がイマイチだったというより、そもそも日本語の学習データが弱く、2021年以降の最新情報も反映されないので、ほぼテスト以上の意味はありませんでした。
ChatGPT(とGPT-3.5)の主な制限や注意点
ChatGPTって、凄い!素晴らしい!こんなことにも答えてくれる!そんな話ばかりが溢れていますが、注意点がいろいろあるので、そっちをメモしておきましょう。
- 与えた問いや指示の文章を解析して、確率が一番高い文章を返しているだけなので、知性ではない(それでも凄い品質!)。
- 時々、とんでもない間違った回答をしれっと混ぜてくるので、油断ができない。
- 2021年以降の最新情報は学習されていないので、答えを間違える確率が上がる。
- 言語モデルでは日本語の学習データが弱い。同じ質問をするにしても、英語の方がより上質な答えが得られる。もちろん、日本ローカルなネタも十分にはカバーできていない。
- アルファベットに比べて、日本語を処理するコストが高い。
- 効果的な答えを得るには、ある特定の流儀、メソッドがある。呪文やプロンプトと呼ばれることもあり、これはもうプログラミング!
- 最近、全世界的に人気なので、動作が遅かったりエラーになることも(ライブデモをする人はご注意を)。
- アメリカの調査会社ユーラシア・グループが発表した「2023年の世界の10大リスク」では、「ならず者国家ロシア」、「『絶対的権力者』習近平」に続いて、AIで自動生成されたフェイクコンテンツは「大混乱生成兵器」として、ワースト3位!
今回の雑談のレギュレーション(?)
ChatGPTは、対話を通じた文章生成AIなので、雑談もできるといえばできます。ただ、明確な指示を与えれば、それに対する答えとして、確率的に最も高い一般的なフレーズを膨大なデータベースから並べて返すに過ぎません。そのため、会話をちょっと広げたり、少しシフトさせるような返しは得意ではないと感じています。
そのため今回の記事は、自然な雑談っぽい雰囲気になるように、全面的にリライトしています。関係者の皆さんとの雑談も思い出して交えたり、いかにもChatGPTが丁寧に答えているところは、私がそれっぽく書いていたりもします(AIの意味が全然ないぞw)。
雑談の大半は日本の教育システムや働き方など、結構な大風呂敷になってしまいましたが、そもそも私は教育現場の人間でも何でもありません。企業や他の教育機関でのITトレーニングの経験こそあれ、非常勤講師として関わっていただけなので、限られた時間と接点から感じた範囲の肌感覚に過ぎません。そんな前提を踏まえた上で、ご覧いただければ幸いです。
「放し飼い」してもらった自由なシラバス設計
約2年半の専門学校での授業を振り返って、どうでしたか?
そうですね、長かったような、短かったような…。自慢するようなことでもないんですが、コロナ禍にも関わらず、罹患も欠席もせずに何とか完走できたことは、常識に欠ける社会人として私自身のトレーニングでした。遅刻はギリギリで回避したことが一度だけあったものの、欠席は一度もしませんでした!
最初にいうのがそれですか…学校は、博多駅前にあるんですよね?
はい、専門学校Adachi学園さんで、最初の半年が九州スクール・オブ・ビジネス、後の2年は九州ビジュアルアーツさんにお世話になっていました。
具体的に、どんな授業を担当していたんですか?
タイトルとしては「編集企画」でした。文章作成としてのライティングや校正・校閲を中心に、メディアやソーシャルネットワーク、広告、コミュニケーション、プレゼンテーション、マーケティングなど、幅広いテーマを扱いました。
また、デバイスやセキュリティーなどの基礎や、今の社会で重要なキーワードや、本の紹介も交えていました。結局、なぜ、何のために、どこで書くか…などを考えると、網羅的な話を抜きにできませんからね。
いつものクドい内容だったわけですね。シラバスや資料はどうしたんですか?
シラバスは自由に提案し、設定させてもらいましたし、個人的に必要だと思ったリモート授業も、学校全体のカリキュラムに縛られず、許可していただきました。もちろん、必要な報告は交えつつ、かなり「放し飼い」してもらって助かりました。
ただ、シラバス構成や資料のアップデートが、想像以上にキツかったですね。
アップデートの速度と量がカギ
というと?2年目は、1年目の資料を流用しなったんですか?
もちろんしましたよ。授業で使っていたシラバスや資料は、元々、社会人のITトレーニングに使ってきたモノを、ずっとアップデートしてきたオリジナルの資料ですし。
正直、前年の資料を使って一部を微調整すれば、準備や進行はある程度楽になるだろうから、オペレーションコストがちょっと下げられるな、と期待していたんですが、全然、そんなことはありませんでした。
それはちょっと意外ですね。どうしてですか?
やはり、社会の変化が激しくて速いからです。
例えば、メディアの話で新聞各紙の読み比べをしながら、『各紙が同じ見出しを一斉に打つなんて、大災害や大事件でも起きない限り、そうそうない』という話をしていたら、安倍元首相の銃撃事件の翌朝にはそれが現実になってしまいました。マスメディアの影響力の低下について話したら、「週刊朝日」がついに休刊したり。
現実を呼び込んだようなことが起きていた、と。
そうなんです。日本のジェンダーギャップ指数の話の流れで、ディストピア社会を描いたマーガレット・アトウッドのSF小説『侍女の物語』と映画を紹介したら、アメリカバージニア州の学校図書館で禁書処分になりました。現代社会のキーワードの解説でも、「リカレント教育」だけでなく急に「リスキリング」が取り上げられることが増えました。
事例のアップデートが常に必要というか、それまでの現実や常識を新しい出来事が上書きするようなことが日々起きるので、とにかく短距離ダッシュを繰り返しながらマラソンを完走するようなアップデートが必須でした。
そう考えると、1年前の資料もそのままでは使えないのはわかります。
1年といわず数ヶ月で、状況がガラッと変わってしまうこともありました。E.マスク氏のTwitter買収などはその一例。もちろん、折角更新してきたのに、使えなくなった資料もあります。これだけ変化の速度が速く、影響も大きい昨今、指導する側のノウハウやナレッジのスピーディーかつ的確なアップデートが避けられません。
現代人は、毎日、情報のアップデートに晒されていますからね。
学生さんたちが全員iPhoneユーザーだったんですが、2023年はiPhoneがリリースされて16年。彼らは、物心がついた頃にはすでにスマートデバイスが身近にあったわけです。その当時に比べると、今の私たちが接する情報量は爆発的に増え、変化の速度も圧倒的に高速になっています。
実は、授業が終わった後、すぐまた次に使う予定がなくても、地味にアップデートを繰り返しています。
急速な変化といえば、2022年からAIを使ったコンテンツ生成サービスは、大きな話題になっています。
2022年の夏以降、今もホットですよね。MidjourneyやStable Diffusion、DALL·E 2、そしてChatGPTが爆発的に盛り上がっています。画像編集だけでなく、ライティングやビデオ/オーディオ、プログラミングまで、今、クリエイティブ系の専門教育で、AIに全く触れないシラバスはあり得ないでしょう。指導者側のノウハウやナレッジが更新されていないと、最新の情報を正確かつ効率的に学ぶことができません。
なのでこの記事も、一部にそれを使ってみているわけです。今、ライティング授業のシラバスを設定するなら、間違いなくChatGPTを最初から使うでしょう。
Z世代の学生さんたちとのコミュニケーション
ところで、高校を卒業したばかりの若い世代とのコミュニケーションはどうでしたか?
当初は、今振り返っても本当にボロボロでした :'(『社会人向けのITトレーニングのメソッドが、全然通用しない!』『デジタルハリウッド(デジハリ)でしゃべっていた頃に来ていた社会人学生さんたちとは、全く違う!』と、いろんなところで感じていました。
私とは、親子以上に離れた世代です。それぞれの興味・関心や得意・不得意を知ったり、速度・深さ・広さを調整するより先に、共通言語を探るところから必要でした。組織の教育担当者や中間管理職、保護者の苦労も、ほんの少しだけ理解できたかもしれません。
それなりに、苦労や苦悩もしてたんですね。
校長には『ね?うまくいかないもんでしょう?』って、よくイジられてましたw とはいえ、新しいチャレンジを楽しんでいたのも事実です。世代で区切るのもちょっとアレですが、Z世代の複数の人たちと定期的に接する機会は初めてだったので、本当に貴重な体験でした。
私自身、失敗したり、最後まで上手くいかなかったことも多かったですが、できたことは素直に自己評価しておきます。学生さんたちにも、言ってきたこととまんま同じですけど 😛
企業の新人教育などでも聞く話です。
そうですね。しかも、デジハリさんの頃と違って、仕事に就いた社会人経験そのものがないわけです。授業料だって、全員が自分で働いて払ってるわけじゃない。やりたいことが何なのか明確になっている人も少ない。その意味では、緊張感は低くなりがちだったかもしれません。
やはり、よくいわれるZ世代的な指向も感じましたか?
Z世代がそうなのかどうかはわかりませんし、私自身、自分が世代で勝手に分類されるのもあまり好きじゃないので、かなり乱暴な印象だという前提ですが…。
『失敗なんてないんだから、学生という立場と学校、私を最大限使い倒そう!』とは、何度も繰り返していました。でも、失敗や挫折を極端に怖がって、先に正解を知りたがる傾向は感じましたね。批評を、批判や個人攻撃だと過剰反応しがちな人も。なので、あくまでも楽しく繰り返しながら、いろいろな経験をすることを常に意識していました。
ただ、危機感が薄かったり、チャレンジするマインドの低さを糾弾する気にはなれません。
それは、どうしてですか?
彼らがそう教育されてきたからです。物心ついてから、凋落する一方の社会の状況しか知らないわけです。いろんな先の状況が見えてしまっている(と思い込まされている)中で、リソースやリスクは自己負担せよ、失敗しても全て自己責任だというのは、厳しいと思います。
昨今、本当にくだらない校則の問題がようやく指摘されるようになりました。しかし、義務教育では、従来からの組織のルールを疑わず、それに従って、個性は許可された範囲でだけ、求められるように出すことが求められるわけでしょう?
まして、専門学校はわずか2年間。
そう。4年生大学で例えると、1+2年ではなく、1+4年なのだと感じました。この2年間で、付き合う周囲の人たち、時間の使い方、人によっては住む場所まで、大きく変わるわけです。何だかよく分からず激変する環境に翻弄されながら、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)アピールで「盛り気味」のエントリーシートを書き、連日のリモート就活に臨むのは、かなりストレスフルだと思いますよ。
上手くいかなくても当たり前ですし、それを受け止められないのは、そうなるように仕向けてきた私たち上の世代ですから。
「日本の高等教育が直面する課題」的な風呂敷
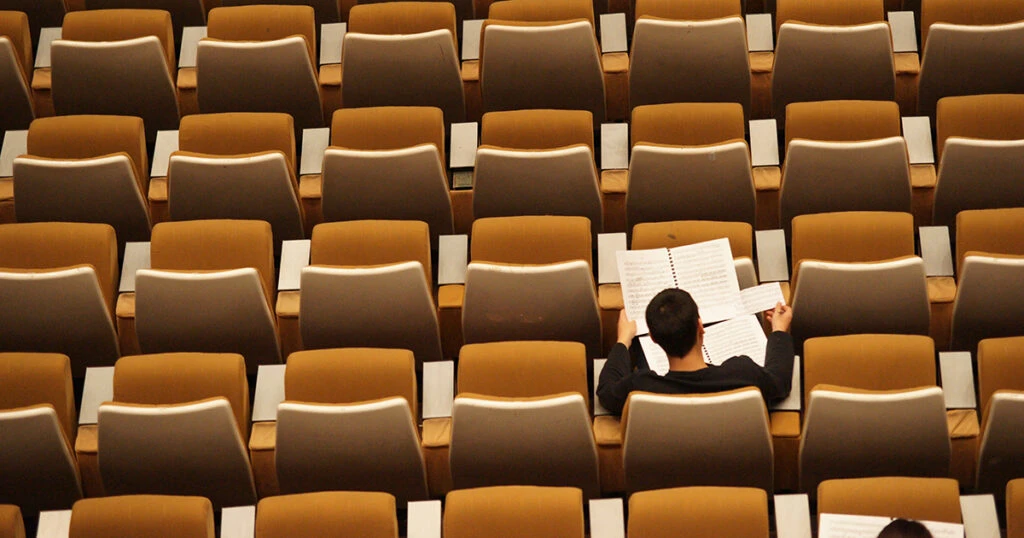
一般の専門学校の状況については、何か感じることはありましたか?
何年も前ですが、博多地区の町おこしイベントで他校も含めた接点がありましたが、現状はどうかわかりません。ただ、福岡という都市は、『東京は不安だけれど、福岡だったらいいか…』という消極的な妥協として、大学や専門学校が選ばれる現実は、今もあると思います。
なるほど。広島の高校生で、東京ではなく大阪の学校へ進学する生徒もいるとも聞きます。
そうですね。福岡に限らず、地域の専門学校を選択する若い世代や保護者たちは、保守的な意識が強いような気がします。福岡の博多駅や天神地区の学校の場合、実際に九州各地や西日本の学生が集まってきていますし、そこへ新型コロナウイルスのリスクも影響して、遠隔地への進学を心配した保護者や本人もいると思います。
これも先ほどの、保守的なマインドに通じるんですかね?
日本の労働環境は、未だに4月の新卒一括採用だったり、解雇が制限されて雇用の流動性が低いですよね。労働環境が変わらないのに、学校だけ変わるわけにいかないのは当然でしょう。
学校法人にしても、ビジネスを成立させていく以上、就職率や就職先をアピールしなければならなりません。しかし、全員が同じようなリクルートスーツと髪型に身を包んで、「社会に出る」というより「会社に入る」人が「製造されていく」ような現状が、果たして本人たちや、もっというと日本社会にとって、本当にいいことなのか私にはよくわかりません。
ところで、社会人のリスキリングやリカレントが叫ばれる昨今ですが、高等教育の現場から見てどうなんですかね?
さっきから、ChatGPTが苦手な、日本の今の話に持っていこうとしてますよね?w この2年半、教育関係のWebサイトや書籍を読み漁った程度ですし、日本の高等教育の現状を語れるほど理解していません。
ただ、一般論として感じるのは、仕事ですぐに役立つスキルを学ぶことが望まれている雰囲気です。労働生産人口は減る一方で、どこも人手不足ですし、過去には『大学を専門学校化するな!』などとまで言われていたのが、今や『役に立つ研究成果にしか金を出さない!』ですからね。
映画が早送りで見られたり、コスパよりタイパ(タイムパフォーマンス)が求められる時代です。
そうなんです。でも、仕事ですぐに役立つスキルを学ぶことは、課題を発見して研究する高度な教育とは相容れないと思いませんか?簡単に手に入るモノは、すぐに使えなくなるもの。社会の変化に対応するためには、実践的なスキルと問題解決能力、創造力などを兼ね備えた教育が求められているんだなってことは感じます。これは、全ての現代人の課題ですけど。
雇用形態や労働環境の流動化も指摘されています。
確かに、日本特有のメンバーシップ型から、グローバルスタンダードのジョブ型へと、少しずつシフトしています。しかし、働きながら学びたい人たちのバックアップは不十分ですし、自分自身で本当に学ぶことが必要だと気付いた時の、アクセシブルな教育システムもありません。そもそも、他者とは違う選択をしたり、失敗したときの再チャレンジの手段が限定的な社会で、すべての負担や責任を個人に求めるのは厳しいと思うんです。
VUCA時代の教育をどうするか
それは確かにそうですね。日本の高等教育には、いろいろな課題が指摘されて久しいですし。
はい。主に、以下のような課題が指摘されているようで、よく見聞きします。
- グローバル化に対応した教育の見直し:迅速な技術革新や国際競争の増加に対応するため、教育内容や方法の見直しが必要
- 評価の不正確さ:学校の評価システムの正確性や透明性
- 就職困難:一部の卒業生が直面する就職の困難
- 資金不足:独自の財源を確保する必要あり
- 質の低い教育の問題:一部の学校では、教育の品質が低い
18歳人口は今後さらに減少し、学校法人の経営も厳しくなっていくでしょう。統廃合も進み、文系の短大なんて間違いなく消えていく。学生の数を水増しするために、留学生を大量に受け入れて問題になるような学校すらありますよ。今後、淘汰が進んでまともな組織をちゃんと残さないと、質は上がるはずがありません。
先生という仕事は、どこも本当に忙しいみたいです。
現場が疲弊しているのは、何のためなんだ!?って気はします。教師のサービス労働や賃金は先進国で最悪ですし、そりゃTwitterで #教師のバトン が炎上するのも当たり前。日本のエデュテック(教育領域のテクノロジー)でDXに成功したような話も、ほとんど見聞きしないような。
どれも納得せざるをえませんが、改善するには相当な覚悟が必要な気がします。
でしょうね。教育システムは政治と密接に関係しているので、残念ながら、簡単には変わらないと思いますよ。少子化することが分かっていたにもかかわらず、この数十年、抜本的な改革もされて来ませんでしたし、映画『教育と愛国』を見れば、正しく絶望できます。
専門学校や大学の前に高校、中学、そして小学校…やっぱりそうですよね。
はい、少子高齢化がさらに進む今、日本の高等教育の仕組みそのものが、VUCA(変異・不確実・複雑・不確定)の時代に対応する必要があります。教育システム全体に改革が求められているはずですが、多様な要素が絡み合ったさまざまな制約があります。現代の教育システムを、効率的かつ正確に更新できるか?私は、とっくに時間切れだと思いますけど…。
“Study or Die!” 学ばずにいられない個人ができることとは?
しかし、遅いアップデートが待てない学びたい個人が、できることはあるんじゃないでしょうか?
希望が残っているとしたら、そこでしょうね。
国際的な視点を持った教育や、異文化理解などの分野を学習することで、グローバルな視野を持った人材になるでしょう。今後も教育環境が変化することが予想されるので、利用可能なリソースを活用し、学ぶことにフォーカスすることが大切です。
話がますます拡がってきました。
でも、本当にそう思いませんか?ITテクノロジーの進化によって、世界中の教育を手軽に受けられるようになりました。例えば、人種や貧困のために、低い社会階層にいる子供たちが、欧米の公開授業を無償で受けることで、自由と権利を獲得できるチャンスは、今まではあり得なかったことです。日本の若い世代でも、上質な真の教育に触れて学習できるチャンスは残されていると信じたいです。
ただし、低所得層は上質な教育に必ずしもアクセスできないデジタルディバイドや、長時間労働は学習意欲の阻害要因になるという現実、英語と比較した日本語という言語のディスアドバンテージは、立ち塞がっています。
学習塾のリモート授業を受けている姿も珍しくありません。
私は初回の授業でいつも、『勉強したいだけならYouTubeでいいじゃん!大抵、無料だし。何で、わざわざココに来てるんだっけ?』と問いかけていました。完全オンラインの学校もいくつかありますし、元々、放送大学も昔から一部のニーズに合っていました。
そこへ、新型コロナウイルスが感染拡大が重なった、と。
そうです。憧れのキャンパスライフを思い描いていたのに、誰とも会えず、雑談もできず、学習どころか生活意欲も持続できない。地方から都市部へと出てきて、バイトと部屋の往復、友達もできない。これじゃあ家で独りYouTube見ていたのとほとんど何も変わらない!
結局、心に深い傷を負って学校から去っていく学生も多いと、メディアでたびたび報道されてきました。これは本当に悲しいことですし、若い学生に限ったことでもなく、就職したばかりの世代でもあるようです。
学習も仕事も、結局は対人濃厚接触による意思疎通
完全にオンラインに振り切れるわけでもなく、出校するスタイルも戻ってきていますね。
大手テック企業の一部は、出社に回帰したり、リモートと出社のハイブリッドになったり、コロナ禍4年目のワークスタイルも変化しています。コミュニケーション上のデメリットは、リモートのメリットではカバーしきれないことに、一部の企業が気付いているんだと思います。
ところで、リモート授業は上手くいったんですか?
Microsoft Teamsって、何であんなに使いづらいんですかね…。それはそれとして、学生は皆、意見交換や議論を経た合意形成がすごく苦手な印象でした。オフラインの教室ならまだしも、オンラインでカメラオフだと(カメラへの抵抗感は根強くて)、ますますそれが不得意だなという印象を抱きました。これも、彼らのせいじゃないんです。そういう教育を受けてきたから。
よく口にしている「コミュニケーション解像度」というヤツですね。
はい。教育って、人間同士のコミュニケーションや学習に対するモチベーションと切り離せませんし、教室での授業形式は長年の伝統と実践に基づいているみたいです。でもオンラインだと、これが再現できない。
私はいつも「コミュニケーション解像度」といっていることなですが、オンラインはそうでなくても荒い解像度を補完する演出が不可欠なんですけどね。学生同士の直接的な関係性や、教師と学生の一対一の指導、グループワークなどはハッキリと学習効果が落ちていました。
高校生などさらに若い世代は、これからどのような教育を選択すればいいと考えますか?
やはり、自分のキャリアや将来に向けた目標を明確にすることが大切でしょうね。志望する分野のトレンドや将来性を調べ、自分に合った教育プログラムを選択することも重要だと思います。さらに、自身のスキルセットをアップグレードするために、海外を含むオンライン学習や留学なども検討した方がいいでしょう。
最終的には、自分自身の情熱やスキルを活かし、目標に向けた学習を進めていくことが大切という、何だか当たり前の話。保守的な考え方に囚われず、自身のキャリアアイデアに基づいて、教育を選択していくことがますます重要ですが、学びたい情熱があるかどうかは世代に関係ないですよね。
総じて、自身にとっても有効な体験だったわけですね。
もちろんです!学生さんたちや学校関係者の皆さんに、少しでも役に立てたなら、これほど嬉しいことはありませんが、自分にはプラスだったと思えます。『伝わったことが、伝えたこと』を信条とする身としては、結局、上手くできなかったりヘタだったことで、改善や解決の視点を得た、私が一番学習した機会でした。
架空の雑談をやってみましたが、相手から予期しない質問が来たり、見解が少しズレることによる拡がりもさほどなかったので、費用対効果は微妙…。というか、時間は結構掛かったので、全然効率的ではありません。
それでも、実際に以前この型式の取材を受けたことがある身としては、目的や使い方次第ではこれでアリかもしれません。反射板(リフレクター)としては、それなりに優秀だと感じました。ここに、いろいろな統計資料やメディア報道、第三者の質問や回答が混ざれば、それなりの形にはなりそうな気はします。
『私でなくても書けること』や『がんばって書かなくてもいいこと』は、AIに任せてしまえばいいんですが、それはつまり、その指示を的確に出せるスキルが要るということです。
ただ、重要なのは編集ですね。誰に、何のテーマについて、どんな魅せ方で書いてもらうかの設計です。ここはまだまだ人がやった方がよさそうだと感じています。その一方で、構造を見直すとか、導線を意識したり、段落を整理するとか、ファクトチェックやポリティカルコレクトネス的な面の校閲は、AIが十分機能しそうな気がします。
ということで、GPT-3.5を使った文章の生成は、実際の仕事の一部にテスト的に使ってみています。とにかく、未来は想像以上に速く、しかも強烈にやってきそうですよ!公開できる情報はまたアップデートしますので、どうぞお楽しみに 😉