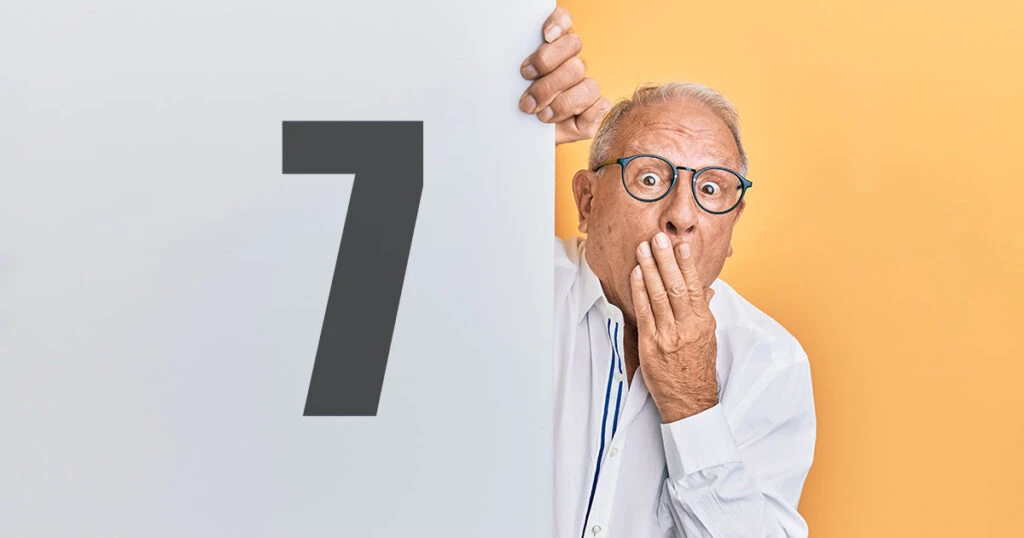
仕事でやり取りする資料や書類を、紙からPDFベースに移行する時の主な注意点をまとめて紹介します。こうすれば着実に【失敗できる!】という、実録ベースの逆説的NG集。非効率な紙ベースを止めたり押印の廃止などを目指そうとする時に、こういったトラップに注意!
私も、『ブレードランナー』のロイ・バティー並みに、いろいろなモノを見聞きしてきました。PDF移行の失敗あるあるを、夜の雨に打たれながらの気分でご覧ください。
パンデミックは、ワークフロー改善の最大のタイミング!だったはず…
コロナ禍でテレワークが拡大して以降、PDF関連の記事がとても読まれるようになりました。パンデミックレベルの激変で、遅まきながらようやく、非効率なプロセスを変えようと本気になった組織が多いんでしょうかね。
ただ、『社印は社外持ち出し禁止という規則だけは、どうしても変えられない』とか、『紙の書類に印鑑を押すためだけの仕事を担う、上司の存在がネックだ』とか、数々のトラップは相当なもの。クラウドの運用に失敗してデータ漏洩をやらかし、FAXと電話に逆戻りするという、本当に情けない自治体もありましたし… :'(
主にどんなことが原因で失敗してきたか、7つにまとめてみたので、自社の状況と照らし合わせながらチェックしてみてください。年度末に間に合えばいいけど…
1. ソフトウェア環境を確認せずにスタートさせる
その人がPDFをどんなツールで生成・閲覧しているかは、千差万別。Acrobatとは限らず、サードパーティー製アプリやChrome用プラグインなど、可能性を挙げればきりがありません。
部署単位でも違うのはよくある話。クリエイティブチームはMacで常に最新版のAcrobat DC、製造や営業部門はWindows版の古いAcrobat Standardなど、珍しくありません。さらにここに、PDFというフォーマット自体の、バージョンによる差異が加わるわけです。
こうして、ソフトウェアの話をしているはずが、担当者にはなぜかWordのテンプレートについての質問まで押しつけられ、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
2. ハードウェア環境を揃えずにスタートさせる
もちろん、ハードウェア面の環境整備も重要です。会社から支給されたセキュアなデバイスなら、情報システム部門が管理しているので安心(かも)。一方、必要な認証プロファイルだけインストールしていれば、使ってOKというややグレーなルールの組織もあるはず。ただ、家族と共用しているデバイスなどは、かなり危険なケース。じゃあ、個人所有のスマートフォンやタブレットならいいかというと、デバイス管理はパソコンよりも面倒だし。
こうして、会社支給の古いラップトップより、受験生が使うタブレットの方がスムーズにPDFが扱える(人的ノウハウ込み)ことを知って愕然としているうちに、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
3. 教育やフォロー体制を考慮しない
テレワークの推進によって、サポート部門への社内からの問い合わせも増えました。従来は、近くのメンバーにちょっと聞いたりができていたことすら、そうもいかなくなってしまったわけです。
PDFの情報は、Adobe公式のヘルプやFAQが充実していますし、ブログやビデオも豊富です。もちろん、日本語。サポート体制がない組織でも、チームで必要な機能にポイントに絞ってリンク集にまとめたり、使い方やミスしやすい点をドキュメント化したり、動画マニュアルを作っておけば、自分の貴重な時間を割く必要は減らせるでしょう。
でも、最初のそれを誰が作るのか?どうアップデートしていくのか?しかも、学ばない人たちは、学ばない。頼られる方からすれば、そんなことにまでいちいちリソースを削いでいたら、自分の仕事が進まないうちに、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
4. 最低限必要なノウハウやナレッジが共有されない
丁寧な人材教育なんて、今や大手企業でも厳しいわけです。自己学習や問題解決能力がある人材には、参照先が共有さえされていれば、それなりに学習が進みます。現場で役立つ情報がメンバー間で共有されやすい環境があれば、サポートの手間も減り、チームのコミュニケーションのフックにもなります。上手くいけば、一体感にもつながったり。
ただ、ハーアドな成果主義が導入さている組織だと、これは全く進みません。人を助けている場合じゃないからです。こうして、セクト主義や、酷いところになると足の引っ張り合いなどもあり、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
5. 決裁権者や法務部門の了承が得られていない
意志決定層や、それに近い高齢の幹部の説得はなかなかタフです。とはいえ、国や地方都市の行政機関レベルで、押印の廃止が急速に進んだり、テレワークが推奨されているのは、過去になかった追い風。行政機関や業界の動きを見ながら、法務や経理など、関係部門の責任者との足並みも揃えて、ジワジワと既成事実やエビデンスを揃えて、交渉に臨みたいもの。
しかし、最も困難な課題を5番目にあげた理由は、これがクリアされているような組織なら、とっくにペーパーレスに移行しているから!
こうして、『重要な文書はやはり紙でなければ!』という上層部や法務部と、『資料、共有しますね!』といってスクリーンショットを送ってくる新人の板挟みになり、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
6. 受発注相手と調整せずに強引に進めてしまう
『発注元の大手が未だに紙ベースなので、なかなか変えられない』というのも、よくある話。逆に、発注先に対して率先できる立場だったとしても、既存のやり方を強引に変更すれば、無駄な摩擦や作業が増えて、結局、ストレスフルです。
環境が一気に変わることはありません。変えられる関係先から、少しずつシフトしていけば、ノウハウも溜まっていきます。そのためには、関係各所との地道な交渉、その前の個人的な信頼関係が…といっているうちに、年度替わりで担当者が変わって、振り出しへ戻る…
こうして、A社とはPDF、B社とは担当者によりPDFだったり紙だったり、C社はPDFでなくすべてExcelという、別の意味のアクロバットを強いられ、PDFベースへの移行計画は失敗するのです。
7. 紙や印鑑の電子化が目的だと勘違いする
なぜ、紙や印鑑、FAXが捨てられないか?しつこく何度でもいいますが、これは、単にフォーマットやアプリケーションをどう使うか?という現場レベルの話ではなく、組織のワークスタイル全体の話だからなんです。もっというと、その組織が目指す将来像の話。
例えば、FAXを紙ベースからオンラインに変えるのは、短期的な効率化としては間違っていません。大量一括処理やデータとしての扱いやすさ、通信コストの削減など、メリットも沢山あります。しかし、ここで考えるべきスタートは、『そもそも紙や印鑑でなければならない理由は?』のはずなんです。しかし…
こうして、今までやってきたこととこれからの行く先を考えているうちに、担当者はそのまま諦めモードに移ってしまい、PDFベースへの移行計画は失敗するのでした…
紙書類や印鑑からPDFへの移行を進めるために、すべきこと
では、こういういくつものトラップに引っかからないためには、何をすべきなのか?
- 紙書類や印鑑からPDFへの移行は、一気には進まない。最初にある程度揃える範囲と、徐々に浸透させていく範囲を分ける。前者はすぐ全員で、後者は徐々に。
これは、サービスやツールの話ではなく、コミュニケーションの話!むしろそっちを先に、せめて同時に改善すべき。 - 必要なのは、トップダウンの決定と実践。権威の象徴として、国や自治体の動きを背景に説得を試みる。ワークフローの改善は、重要な業務タスクであり、評価基準の対象となることを経営層に認識してもらう。
- 特に、『新しいやり方に変えたくない』『覚えたくない』『失敗して恥をかきたくない』『若い社員に聞きたくない』『教えてほしいといいだせない』人たちを、押さえ込むか、上手く外すか。影響力を持つ人に対して影響力を持つ人を、何とかする(今回に限らない話…)。使えるモノも人も、何でも使って道を切り拓いていくのはサバイバルの鉄則!ただし、適切な監視や観察、ケアは怠らず。
- アプリケーションは最新バージョンにアップデートしておく(制限がない場合)。古すぎる環境は、アップグレードを打診する(予算次第か)。自分で何とかできる人以外には、規定のアプリケーションしか使わせない。必要なら、保存用に使うプロファイルを用意して、任意の目的には必ずそれを使うようにルールを決めておく。
- ハードウェアの運用ルールを確認する。必要に応じてアップデートし、セキュリティーポリシーに従って利用する。リースやリプレイスのタイミングもあるので、ソフトウェアと共に確認。家庭や社外にある周辺機器との接続をどの程度許可するかについても、ルールを決めておく(例:私物のデバイスをつないでいいか?コンビニのマルチコピー機を使っていいか?)。
- 業務に必要なポイントだけに絞ったリンク集やマニュアルを作っておき、内容は適度にアップデートしていく。例えば、Slackチャンネルや社内Wikiなどに、雑談とヘルプチャンネルを用意しておく。ビデオはオススメ。最低限のサポートはしつつ、それ以上は、自主的に問題解決を促す。マニュアル(紙にしない!)の存在を示し、熟読するように促しつつも、質問そのものはしやすい雰囲気を作っておく。
- 関係先の環境を把握し、差異や制限を確認する。無駄のない効率的なやり取りの相互メリットを提案する。
折り紙は、PDFでは作れない :'( 豪雨に打たれる深夜の屋上で、ディストピア世界の詩を吟じているうちに、つい長くなってしまいました。
テレワークがある程度は認知・実践され、出社とのハイブリッドなワークスタイルが普及した今、「実は仕事ができない人材」が明らかになった面もあります。これも、コロナ禍でダメになったのではなく、元々ダメだったのが明らかになっただけ。いちいちPDFで共有するよりも、いいソリューションがあるなら、本当は一気にそれに切り替えたいところですが、こっちはさらなる根回しが不可欠です。
バランスが非常に難しいとはいえ、ワークフロー全体を見直して、時間と範囲を区切り、できる部分から改善していきましょう。少なくとも、自分のナレッジと、職業人としてのライフは常にアップデートしつつ。








